-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
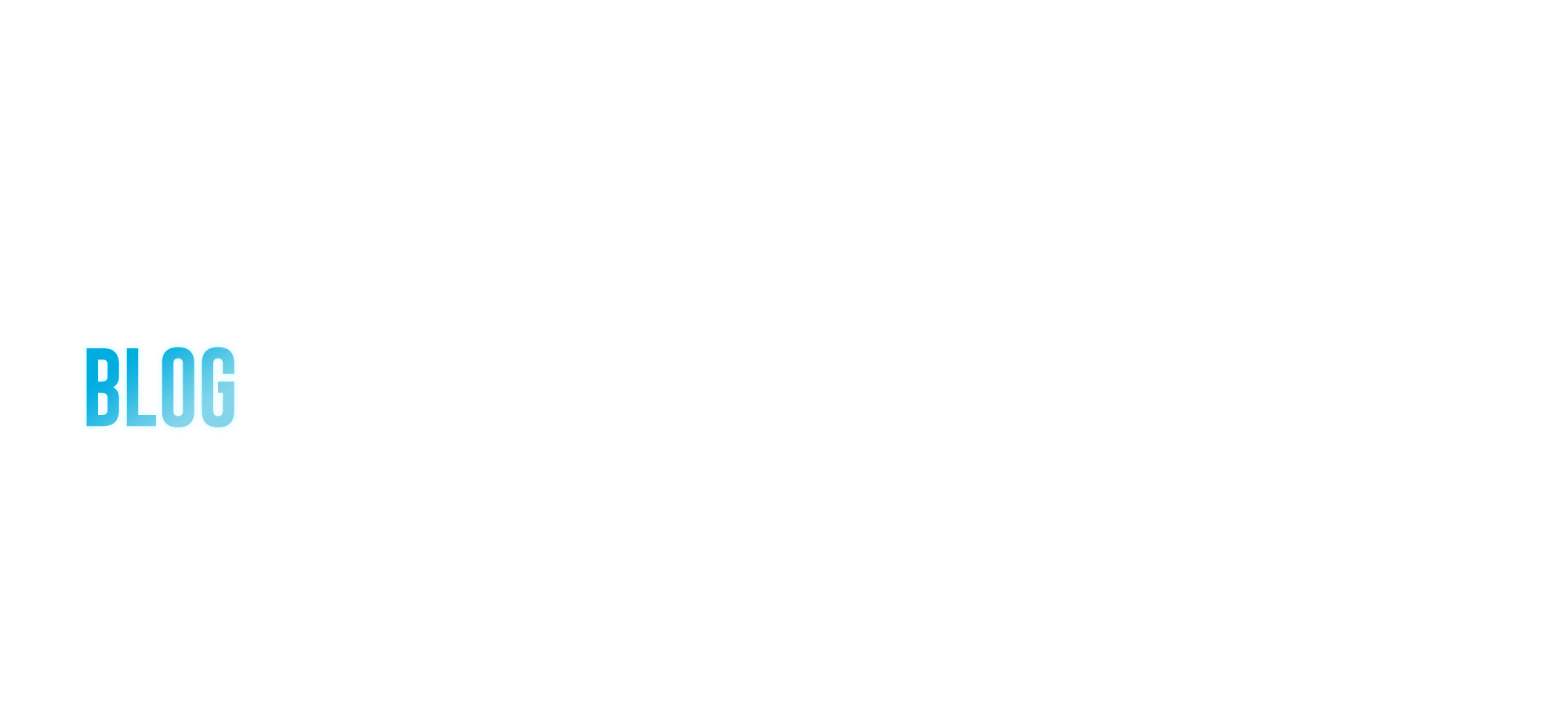
皆さんこんにちは!
機創技研、更新担当の中西です。
前回は船舶修理の現場環境についてお届けしましたが、今回はその「未来」について考えていきます。
海洋産業は今、大きな転換期にあります。気候変動への対応、技術革新、人材不足など…。その中で、**船舶修理という仕事はどう変化していくのか?**未来へのキーワードを一般的な市場での動向とともに紹介します。
近年注目されているのが、“デジタルツイン”技術の導入です。
船体構造や配管図を3Dスキャン・モデリング
点検結果やセンサー情報をデジタル空間で再現
不具合の予測・分析を事前にシミュレーション可能
これにより、従来の「点検してから考える」ではなく、「故障前に対処する」予防型メンテナンスが可能になります。
すでに一部の造船所や修理ドックでは、以下のような技術が導入されています。
自動溶接ロボットによる鉄板補修
**水中ドローン(ROV)**による船底調査
AI判定ソフトによる損傷レベルの解析
今後は、「高リスク作業を人がやらない」時代が来るかもしれません。
国際海事機関(IMO)による温室効果ガス排出削減目標により、修理・保守にも“環境視点”が求められています。
**低VOC塗料(揮発性有機化合物が少ない)**の使用
廃油・廃液の適正処理とリサイクル化
グリーンシップ改造(脱硫装置・バッテリー設置など)
これからの修理は、単なる「直す」作業ではなく、「地球にやさしく直す」時代へ移行していきます。
多くの熟練職人が引退を迎える一方、若手の入職者は少ないのが現状です。
そのため、以下のような新しい育成手法が求められています。
VR技術による修理作業の模擬体験教育
多能工教育(鉄・電気・塗装を横断的に習得)
技能五輪や技能競技会による職人文化の継承
今後は、「知識と技術が見える・教えられる」教育体制が不可欠になります。
海外船籍の修理依頼や、外国人技能実習生の活用など、船舶修理の国際化も進んでいます。
多言語対応の現場マニュアルの整備
国際規格(ISO、IMO基準)への準拠
外国人スタッフとのチーム編成と文化理解
「国内で完結する業務」から「国際水準での対応力」が求められる時代へと移り変わってきています。
船舶修理は、単に古くなった部品を交換する仕事ではありません。
それは、人とモノと海を未来へつなぐ、進化し続ける仕事なのです。
これからの時代、私たちは「安全・効率・環境・国際性」という4つの軸で、さらに高みを目指していく必要があります。
次回もお楽しみに!
![]()